 |
|
 |
 |
1) プラカードや看板などにキャラクターを利用する場合 |
 原則としては著作物の複製にあたるので、著作者の許諾が必要になります。 原則としては著作物の複製にあたるので、著作者の許諾が必要になります。
昨今のように文化祭等の様子がすぐにインターネットで配信可能になった時代では、描かれたキャラクターがインターネット上で公開されてしまった場合、著作者の権利を著しく侵害する恐れがあります。そのため、「授業の過程における利用」としての例外は認められません。 |
|
 |
|
|
2) 演劇の上演や音楽の演奏を行う場合 (著作権法第38条第1項) |
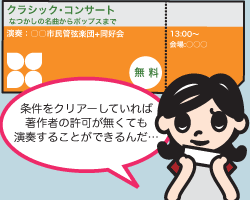 |
原則としては上演権や演奏権等が働くことになり、
著作者の許諾を得る必要がありますが、
 その上演または演奏等が利益を目的としていないこと その上演または演奏等が利益を目的としていないこと
 観衆または聴衆から料金を取らないこと 観衆または聴衆から料金を取らないこと
 演じたり、演奏したりする者に報酬が支払われないこと 演じたり、演奏したりする者に報酬が支払われないこと
という3つのすべてを満たす場合には、著作者の許諾を得ずに演劇の上演や音楽の演奏を することができます。 |
|
|
|
|
 |
3) タレントを呼んで講演会等を行う場合 |
 |
| 講演も言語の著作物になりますので著作権があります。 講演の様子をビデオ撮影して講演後に利用したい場合は、 講演の依頼契約時に講演のほか、あらかじめ想定される いろいろな利用行為について許諾を得ておく必要があります。 |
|
 ビデオ撮影・録音、講演記録の複製・印刷・頒布 ビデオ撮影・録音、講演記録の複製・印刷・頒布 |
| 講演内容をビデオ撮影・録音する場合、そのテープを元にダビングしたり、講演記録を印刷したりして利用する予定があれば、事前に許諾を得ておく必要があります。 講演記録の頒布については、有料・無料にかかわらず講演者が認めない場合や、別に契約しなければならないこともありますが、これらは契約時にはっきりさせておくべきでしょう。 |
|
|
 写真撮影 写真撮影
|
| 著作権法上の権利ではありませんが、講演者は「肖像権」というものを持っています。 ですから、写真撮影についても事前に講演者の許諾を得ておく必要があります。 |
|
 広報のための写真の利用 広報のための写真の利用
|
| 講演の広報のポスター等を作製するときに講演者の写真を利用したい場合は、写真の著作者と肖像権を持っている講演者の両方に対して許諾を得る必要があります。 講演者がPR用の自身の写真を持っている場合も多いので、講演の依頼契約時に広報用の写真の利用許諾も得るようにするとよいでしょう。 |
|
 インターネット上で公開する場合 インターネット上で公開する場合
|
上記   について、講演者から許諾を得た場合でも、 について、講演者から許諾を得た場合でも、   をさらにインターネットを使って情報公開、配信を行いたい場合は、インターネットでどのように公開するかなどを伝えた上で許諾を得ておかなければいけません。 をさらにインターネットを使って情報公開、配信を行いたい場合は、インターネットでどのように公開するかなどを伝えた上で許諾を得ておかなければいけません。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
